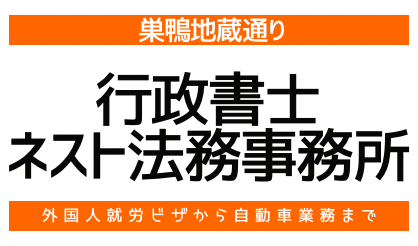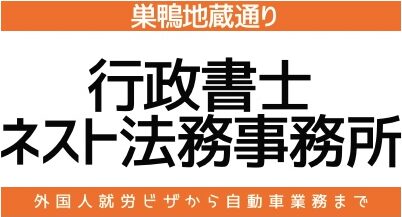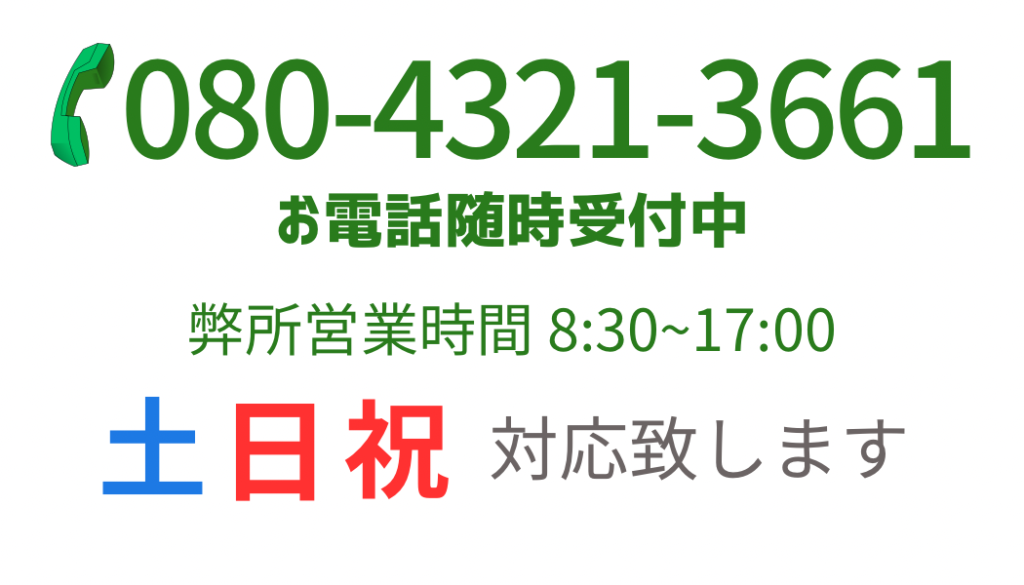特殊車両になったりならなかったりする新規格車について

特殊車両になったりならなかったりする新規格車について
新規格車というものをご存知ですか?
この新規格車も特殊車両通行許可が必要である特殊車両に分類されます。
厳密には、条件に応じて特殊車両になったり、ならなかったりするのが新規格車といえます。
えっ、一体どういうことなの?と感じるかもしれませんが、
まさに新規格車の理解を複雑にしている原因は、新規格車に適用される道路制度によるメリットと一般的制限値を超える車両に必須となる特殊車両通行許可の要件にほかなりません。
この記事ではそれらをひとつづつ順を追って見ていき、着実に新規格車に対する理解を深めましょう。
新規格車に適用される道路制度のメリット
まず新規格車に適用される道路制度のメリットについて理解していきましょう。
新規格車のメリットとして、下の記事で解説した「一般的制限値」の車両総重量20tまでなどの規格を超える場合でも高速自動車国道や重さ指定道路を特殊車両通行許可を取得せずに走行できるという点があります。
一般的制限値についてはこちらを参照ください

ただし、一般的制限値を超過する状態で、高速自動車国道や重さ指定道路以外の一般道を走行する場合には、特殊車両通行許可の取得が必須となってきます。
重さ指定道路とは、車両の総重量20tを超える車両でも走行可能な強度を持つ道路で総重量25tまで走行可能です。ただし、強度的に走行可能であるということで、新規格車以外では特殊車両通行許可が不要という意味ではないので注意!
新規格車には単車と連結車の2タイプがある
それでは、ここからは新規格車自体の話に移りましょう。
まず新規格車には大きく分けて大型トラック(単車)と、トレーラー(連結車)の2タイプが存在します。
しかし、トレーラータイプのものはまだしも、トラックの場合ですと見た目だけではなかなか判別がつきにくかったりします。ですが、安心してください。新規格車という呼称の通り、車両の規格を調べれば正確な判別が可能です。
加えて、ひとつだけ一瞬で見分けられる方法も存在します。
では、トラックとトレーラーそれぞれの新規格車の車両規格を次に見ていきましょう。
新規格車(単車および特例外の連結車種)の規格
トラック(単車)および、特例車種以外のトレーラー(連結車)新規格車の規格は次の通りです。
車両規格面からの新規格車の判断方法ですが、以下の規格内に収まり、加えて、「車両総重量」の項目だけ除いた一般的制限値内に収まるものが新規格車となります。
| 最遠軸距5.5m以上7.0m未満 | 最遠軸距7.0m以上 |
|---|---|
| 総重量22t | 総重量25t |
| ※ 車長9m未満の場合を除く | ※ 車長11m未満なら22t車長9m未満の場合除く |
新規格車(特例適用の連結車)の規格
特例適用されるトレーラー(連結車)新規格車の場合、以下の規格内に収まり、加えて、「車両総重量」の項目だけ除いた一般的制限値内に収まるものが新規格車となります。
| 最遠軸距8.0m以上9.0m未満 | 最遠軸距9.0m以上10.0m未満 |
|---|---|
| 24t < 総重量 ≦ 25t | 25.5t < 総重量 ≦ 26t |
わかりやすい見分け方として新規格車にはステッカーが貼ってある
先ほど述べたように、新規格車と一般のトラックは規格面で違いがあるだけで、基本的に一見すると普通の大型トラックとさほど変わらない外観です。
ですが、それでも1点見分けやすい特徴があるのです。
それは、下の画像のような「20t超」というステッカーが車体の前面に貼ってあるという点です。
こんなステッカーです。

横断歩道などを渡る時、少し注意深く大型トラックの前面を見てみましょう。このステッカーがフロントガラスの右下に貼ってあれば、その車両は新規格車です。
新規格車が特殊車両とみなされる原因は積載重量
今見てきたように、新規格車の総重量は22t〜26tのあいだでした。
基本的に新規格車に最大積載量分の貨物を積むと、22t〜25tほどの重量となります。そのため、新規格車の総重量は特殊車両通行許可が必要となる条件の一般的制限値20tを優に超えてしまいます。これは特殊車両ですね。
新規格車が特殊車両とみなされる原因は積載重量にあるのです。
そのため、新規格車は先の「道路制度のメリット」の項で述べたとおり、高速自動車国道や重さ指定道路を特殊車両通行許可なしで走行することができますが、それ以外の一般道などを走行する場合にはあらかじめ特殊車両通行許可申請を行い、許可を取得しておくことが肝心です。
新規格車で貨物を目的地まで運送する場合、注意したい点がひとつあります。
新規格車は荷物を積載すると基本的に一般的制限値の重量を超えてしまうので特殊車両に該当するので通行許可を取得しなければなりません。しかし、目的地にて荷卸しをして総重量が20tを下回るケースでは特殊車両に該当しなくなります。つまり、このケースでは出発地点から目的地までの片道の特殊車両通行許可を取得すれば足りるのです。