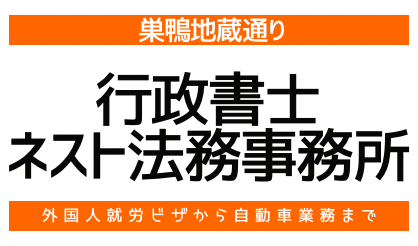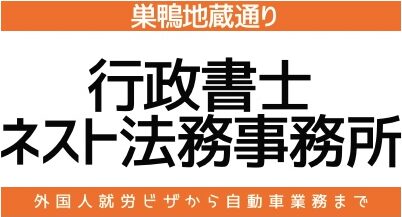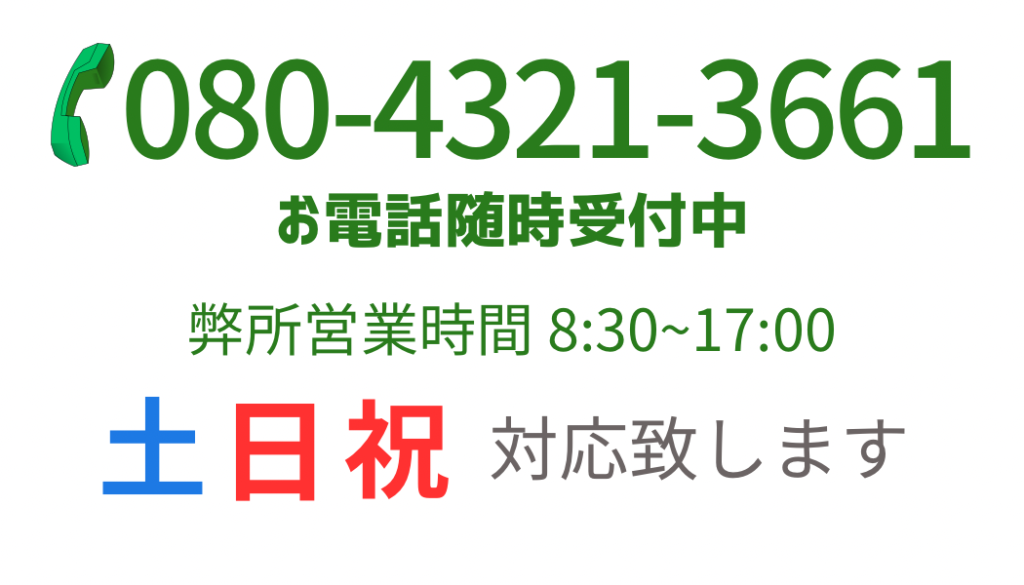在留資格該当性?上陸許可基準?在留資格取得の共通の要件を解説!
どんな在留資格にも共通で定められている要件がある
全29種類ある在留資格には、それぞれ取得するための要件が決められています。
それぞれ、と書いたのは在留資格ごとに要件が違ってくるからです。
ですが、どのような在留資格を取得するにしても共通で定められている要件があります。
この記事ではそれらの共通の要件の見方や読み方を解説していきます。
ほとんどの在留資格に共通する基本的要件は以下の7つになります。
在留資格を得るための手続きに共通の要件
- 旅券・査証の有効性
- 活動の真実性
- 在留資格該当性
- 上陸許可基準適合性
- 在留期間
- 犯罪歴や税金等で特別な問題がないこと(上陸拒否事由非該当性)
- 立証資料の提出
基本的にどのような在留資格でも、つまり活動系の在留資格にも居住系の在留資格にも上記の7つの基本的な要件が共通して定められています。
ひとつづつ順を追ってみていきましょう。
まずは「旅券・査証の有効性」からですね。
1.旅券・査証の有効性
在留資格を得る際の前提として、所持する旅券(パスポート)と査証(ビザ)が有効であることが、上陸の条件とされます。
旅券とは以下に定義されている日本国が承認した外国政府、難民旅行証明書などの証明書を指します。こちらはしっかりとした手続きを踏んで発行されたものであれば問題ありません。
入管法2条5項 旅券の定義
イ 日本国政府、日本国政府の承認した外国政府又は難民旅行証明書その他当該旅券に変わる証明書(日本国領事館等の発行した渡航証明書を含む。)
ロ 政令で定める地域の権限のある機関の発行したイに掲げる文書に相当する文書
査証の定義は一般的に以下のようなものと言われています。
査証(ビザ)の一般的な定義
査証(ビザ)は、日本国大使館又は総領事館の長が、外国人の所持する旅券が真正であり、かつ、日本への入国に有効であることを確認するとともに、発給するビザに記す条件の下において、その外国人の日本への入国及び滞在が適当であるとの推薦の性質を持つものである。また、査証(ビザ)を所持していることはあくまでも、「出入国管理及び難民認定法」上の上陸の為の要件の一つであり、入国を保証する者ではない。
このように、査証は日本大使館や領事館の長が、その旅券が本物であり、日本へ入国に有効であることを確認したものであります。同時に、旅券を所持する外国人が日本へ入国し滞在することの推薦の役割も備えたものとなっています。
また、査証を持っていることがそのまま入国を保証するというものでなく、上陸の為の要件のひとつにすぎません。
そのため、以下で解説してゆく他の要件も同様に満たしている必要があるのです。
2.活動の真実性
申請する在留資格において日本で行う活動が虚偽、つまりウソでないことが条件となります。
「虚偽でないこと」とは、入国審査官が日本に上陸しようとする外国人の陳述や書面、客観的な証拠資料などに基づき、主観的意図と客観的事情を総合的に考慮して判断します。そのため、主張や客観的証拠を照らし合わせて、つじつまが合っており、社会通念に照らして偽りでないと納得できるものでなければなりません。
審査官に疑義が生じた場合、本当のことを言っていたとしても「真実性がない」として不許可になる場合もあります。
3.在留資格該当性
在留資格ごとに、その在留資格で出来る活動が定められています。
例えば、「家族滞在」の在留資格では、在留資格該当性として定められているのは「別表第一の在留資格をもって在留する者の扶養を受け、配偶者又は子として行う日常的な活動」というような具合です。(外交、公用、特定技能1号、技能実習、短期滞在、研修、家族滞在及び特定活動を除く別表第一に載っている在留資格、という意味。)
在留資格 【家族滞在】
外交、公用、特定技能1号、技能実習、短期滞在、研修、家族滞在及び特定活動以外の別表第一の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける「配偶者」又は「子」として行う日常的な活動。
このように「在留資格ごとに定められている活動の類型」を在留資格該当性と呼びます。
先の説明は【家族滞在】についての「在留資格該当性」でした。
つまり、他の在留資格たとえば【経営・管理】であれば異なる在留資格該当性が定められているのです。
申請人本人がこの在留資格該当性に該当しない場合、当然家族滞在の在留資格は許可されません。これは当たり前ですよね。
どんな場合が在留資格該当性に該当しないケースになるの?
これは【家族滞在】の在留資格を申請する本人が、すでに在留している扶養家族の扶養を受けていない場合。
日本で扶養する配偶者や親がパートナーや子どもを扶養する能力が足りない場合。
あるいは、扶養を受けるのが配偶者や子どもでない場合
などが挙げられます。
また逆に、この在留資格を申請する本人がこのような活動に従事しない場合はどうでしょう?
そのような場合もまた、たとえ扶養を受け、実際に結婚していたとしても、「家族滞在」の在留資格を許可されることはありません。
どんな場合が活動に従事しないケースになるの?
これは【家族滞在】の例でいえば、
申請人本人が正社員として就職して毎月20万以上安定してお給料をもらっているような場合など
が考えられます。これは在留資格該当性の「配偶者または子として扶養される」という要件を逸脱してしまうだけでなく、加えて「扶養された配偶者や子として行う日常的な活動」ではなくなってしまいます。
そのため【家族滞在】の在留資格該当性に該当しない、ということになります。
【高度専門職2号】・【永住者】は在留資格該当性から除外されている
【高度専門職2号】・【永住者】の方は在留資格該当性から除外されています。これらの在留資格は、他の在留資格から変更許可申請を行うことではじめて取得することが可能となる在留資格だからです。
また、【特定活動】や【定住者】の在留資格は「告示」という、すでに類型化・パターン化されたものに該当する場合のみ在留資格該当性が認められます。
4.上陸許可基準適合性
「上陸許可基準適合性」とは、名前の通り本来、海外に住んでいる外国人を日本に呼び寄せ、就労や留学などをはじめる場面で用いられるものです。(詳しくは「在留資格認定証明書交付申請」に関する記事「海外の外国人を日本に呼び寄せる場合の手続き」をご覧ください)。
簡単に言えば、外国人がある在留資格を持って日本へ上陸するためにクリアすべき基準となっています。
この基準も、在留資格該当性と同じように、それぞれの在留資格ごとに異なって決められています。
この「上陸許可基準適合性」は、すでに在留資格を許可されて日本に住んでる外国人が、在留資格を変更する場合(在留資格変更許可申請)や更新する場合(在留資格更新許可申請)にも、それぞれクリアすべき基準として用いられます。
つまり、海外に住んでいる外国人を日本に呼び寄せ、就労や留学などをはじめる場面ではもちろんですが、在留資格を変更する際や更新する際にも、変更・更新する在留資格ごとに定められている上陸許可基準適合性を満たしているかチェックして、適合することを立証する必要があるのです。
「在留資格該当性」と「上陸許可基準適合性」。これが次の「5.立証資料の提出」につながってきます。
5.在留期間
申請に係る在留期間が、在留資格に応じた期間である必要があります。
6.犯罪歴や税金等で特別な問題がないこと(上陸拒否事由非該当性)
ここまでで在留資格該当性と上陸許可基準適合性に適合していることを無事立証できました。
最後の4つ目の要件を満たす必要があります。「犯罪歴や税金等で問題がないこと」と書きましたが具体的に重要となる点は以下の7つになります。
これらに特別な問題がなければ、在留資格の変更や更新する相当な理由があるとされます。
これを「相当性がある」と表現します。
- 犯罪歴
- 税金の滞納
- 加入義務のある健康保険や年金などへの未加入・未払い
- 届出の未履行
- 所属機関の経営の安定性・継続性
- 外国人採用の必要性
- 申請内容の信ぴょう性の有無
犯罪歴
入管法で定められている犯罪歴などがあると在留資格を得ることができません。
特に「上陸拒否事由」に該当すると、在留資格認定証明書交付申請が交付されない事態になります。
つまり、日本に上陸できないということになります。上陸拒否事由の代表的なものは次の2つのものがあります。
入管法第5条第1項第4号
日本国又は日本国以外の国の法令に違反して、1年以上の懲役若しくは禁錮又はこれらに相当する刑に処せられたことのある者
これはとても重要な法令になります。
日本はもちろん、日本以外の国で1年以上の禁錮や懲役刑の判決が確定してしまえば、何年経過したとしても日本には入国が許可されない。という文面です。執行猶予がついていても同様に許可されません。
もうひとつ代表的な上陸拒否事由となる法令をご紹介しましょう。
入管法第5条第1項第5号
麻薬、大麻、あへん、覚せい剤又は向精神薬の取り締まりに関する日本国又は日本国以外の国の法令に違反して刑に処せられたことのある者
薬物の前科がある外国人も、刑に処せられてしまったことのある者は日本に上陸できません。
この2つの法令は日本で暮らす外国の方にとって、とても重要なので覚えておくことをおすすめします。
税金の滞納
納税義務を果たしていない場合、在留資格の変更や更新が認められない場合があります。
言い換えれば「相当性がない」と判断されてしまうことがあるのです。
ですから、住民税などはできるだけしっかりと納めましょう。
加入義務のある健康保険や年金への未加入
加入義務のある健康保険や国民年金へ未加入も、同様に「相当性がない」との判断になる可能性があります。
法人などの組織を運営している場合、社会保険などへの加入も必要となります。在留資格【特定技能】の場合は、所属先の機関が労働や社会保険、税に関連する法の規定を遵守していること、という要件もあったりします。
届出の未履行
こちらは、たとえば結婚・離婚や死別した場合、あるいは転職し会社を変えた場合などに届出をしっかりしているかなどが該当します。しかし、この届出を行っていないだけで不許可になるということは稀です。それよりも届出をしないことによって、在留期間の許可が短くなることが多いです。
所属機関の経営の安定性・継続性
所属する会社や運営する法人などの財務状況が悪いと経営の安定性・継続性がないとして申請が不許可になることがあります。特に【経営・管理】の在留資格を申請する際にこの内容が重視されます。
外国人採用の必要性
所属する会社などに外国人を採用する必要性があると認められないと、相当性があると判断されない。つまり許可が下りない可能性があります。通訳・翻訳業務に従事するということで入社し在留資格を取得しようとする場合で、取引先の企業の従業員に外国人がいない場合、通訳・翻訳の業務をすると認められないという理由で不許可になったりします。
申請内容の信ぴょう性
在留資格認定証明書交付申請や在留資格の変更・更新では、申請が虚偽のものでないことが要件となります。仮に申請内容に虚偽があると認められるときは申請が不許可になる可能性が高いです。
具体的にどのような場合に申請内容が虚偽だとされてしまうのでしょうか?
それは、
- 過去に提出した履歴書や在職証明書などの記載と、今回提出する書類の間に矛盾点があるケース
- 申請人や所属先の機関などが、過去に虚偽申請をしたようなケース
などが挙げられるでしょう。
特に1では、提出した書類の間の矛盾点を解消することで許可になる可能性があります。つまり、過去に出した書類と現在提出する書類の間に存在する距離。これをつなぐ書類を疎明資料として添付することで矛盾点が解消されます。その結果、許可につながりやすくなるでしょう。
7.立証資料の提出
実際に「在留資格該当性」にちゃんと該当し、「上陸許可基準適合性」もクリアできている。
「これで安心して在留資格を取得できるわ!」と、いいたいところですよね。
でも、まだ終わりではないのです。
「在留資格該当性」に該当し、「上陸許可基準適合性」にも適合しているという事実を、資料を提出することによって客観的に証明する必要があります。この証明がなければ在留資格は許可されないのです。
そのため、在留資格該当性と上陸許可基準適合性に適合していることを証明するのに役立つ書類を集め、作成するのが大切なポイントとなります。
入管や法務省がホームページに記載している提出書類リストがあります。
そこに載っている書類をすべて提出したからといって、在留資格該当性と上陸許可基準適合性に適合していることを証明できていなければ、まったく意味がないので注意しましょう。場合によっては不利になり不許可になる可能性も大いにあります。
重要なのは、在留資格該当性と上陸許可基準適合性に適合していることを証明することです。
入管や法務省がホームページに記載している提出書類リストはあくまで基本的な書類として捉えましょう。基本的な書類にどのような書類をプラスして、より要件に適合しているということを証明できるかがカギになるのです。
在留資格該当性と上陸許可基準適合性に適合していること証明するため、新たに自分で文章を考え、書類を作成する必要性もあるでしょう。このような立証資料は、証明する事柄に向かって一点に集約するように論を重ね、まとまった説得力ある資料を効果的に作成することが非常に重要となります。
そのため、日本語のちょっとしたニュアンスのちがいでも、審査官にいらない疑問を生じさせたりしてしまいます。言葉の使い方、言い回しひとつで、証明したい事項の方向性が間違った方向に進んでしまう危険性が非常に高いです。
ですから、自分で証明書類を作成するという方は、一字一句入念にチェックをして作りましょう。