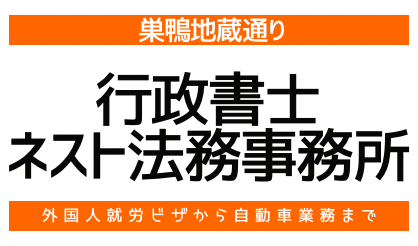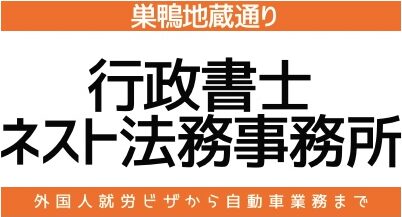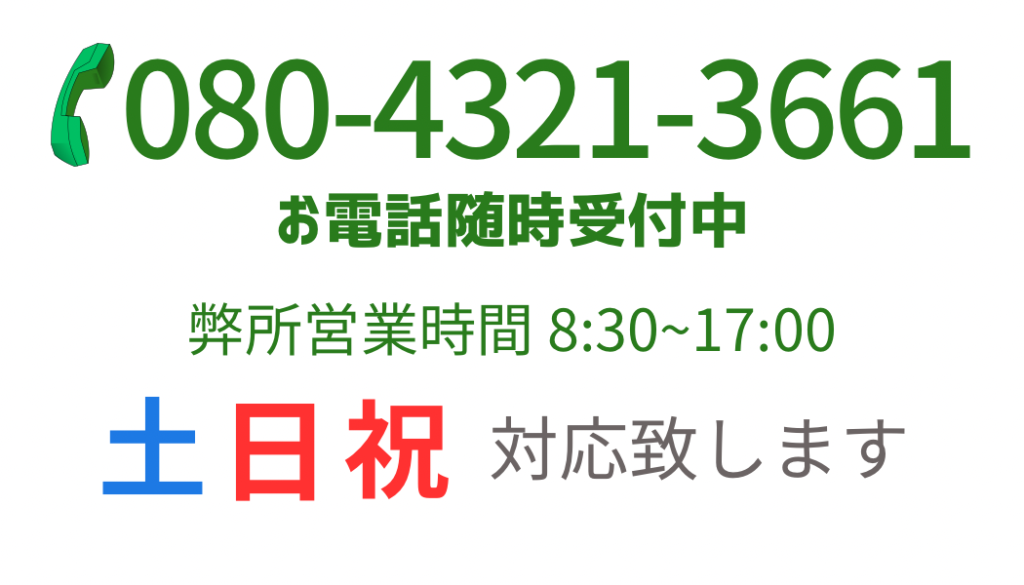在留資格「定住者」から永住するケース
在留資格「定住者」とは?
まず、在留資格のひとつである「定住者」について簡単に説明しましょう。
定住者とは、在留資格のひとつです。具体的には、連れ子として日本に来た人や、父か母が日本人だった人の間に生まれた子ども、つまり日系人の方、永住者の在留資格で日本に在留する両親が本国から、扶養する未成年で未婚の子どもを呼び寄せる場合などに与えられる在留資格となっています。定住者という在留資格は、このように複雑な条件下にある外国人に対応できるように、他の身分系在留資格の補完的役割を果たしています。
そのため、在留資格該当性および上陸許可基準適合性が比較的複雑なので注意が必要です。
定住者の在留資格(ビザ)についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
定住者の在留資格を取得できる方
- ミャンマー難民
- 日本人の子として生まれた日系2世、3世の素行が良い者
- 日系2世、3世で「日本人の配偶者等」の在留資格で在留する者の配偶者
- 1年以上の在留期間を指定されている定住者の配偶者
- 日本人、永住者、特別永住者、1年以上の在留期間を指定されている定住者の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子
- 日本人、永住者、特別永住者、1年以上の在留期間を指定されている定住者の扶養を受けて生活する6歳未満の養子
などが該当します。
定住者が永住するために満たすべき要件
次に定住者の在留資格から永住申請する際の要件を見ていきましょう。
定住者から「永住者」になるための3つの要件
- 素行善良要件
- 独立生計要件
- 国益適合要件
以前紹介した、基本的な永住の為の要件と同じですね。
ですが、定住者から永住者になる場合は、この3つの要件の内容が、基本的な永住のパターンと少し異なりますので注意が必要です。
早速、ひとつづつ見ていきましょう。
定住者が永住申請する際の素行善良要件
① 素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。
出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和元年5月3日改定)」より
だいたい一般的な「素行」の意味と同じような内容ですね。
「永住者」の在留資格を取得するための要件としての「素行」は大きく分けて次の①と②になります。
素行善良要件の「素行」とは?
- 日本国の法令に違反し、懲役・禁錮または罰金に処せられたことがないこと
- 日常生活や社会生活において違法な行為や風紀を乱す行為をくりかえし行っていないこと
- 少年法24条の保護処分が継続中でない者
まず①から見ていきます。
1. 日本国の法令に違反し、懲役・禁錮または罰金に処せられたことがないこと
こちらはひと言でいえば、悪いことをして処罰されていないことを求められています。
身に覚えがなければおそらく大丈夫でしょう。では、もし処罰されたことがあれば素行善良要件を満たさないことになり永住許可が下りないことになるのでしょうか?
処罰されたことがある場合
処罰されたことのある人でもある一定期間が過ぎれば、要件を満たしているとみなされる可能性があります。
たとえば次のような場合です。
懲役・禁錮 →刑務所から出所後10年過ぎていること
執行猶予付き →猶予期間満了から5年過ぎていること
懲役・禁錮の場合は刑務所から出てから10年が経過していること。執行猶予なら猶予期間満了から5年経過していることが必要です。
罰金・拘留・科料 →支払いを終わって5年過ぎていること
罰金・拘留・科料の場合は支払いを終えてから5年が経過すること。それによって日本国の法令に違反して処罰されたものとしては取り扱われなくなります。
以上で1は終わりになります。
続いて2を詳しく見ていきましょう。
2. 日常生活や社会生活において違法な行為や風紀を乱す行為をくりかえし行っていないこと
2の要件は1の要件である”日本国の法令に違反し、懲役・禁錮または罰金に処せられたことがないこと”に該当しないような軽い法令違反であって、くりかえし違反していない者であることが求められています。
つまり、軽い違反だったとしても、くりかえし何度も注意や警告をされている履歴があるようだとダメということになります。
いちばん多いのは車や自転車の違反
2で一番多いのは車や自転車の違反です。
駐車禁止違反、一時停止違反、携帯電話の使用。あるいは自転車での信号無視や歩行者妨害などが当たります。基本的には過去5年間で5回までくらいならだいじょうぶと考えてよいでしょう。もちろん、少なければ少ないほど良いです。
注意しなければいけないのは「故意な違反」とみられるような場合です。
飲酒運転、無免許運転は軽微な違反ではないので1回でもしてしまうとダメです。
車や自転車の違反を確認するためには「運転記録証明書」を取得する
自分がどのような違反をしたことがあるかわからない場合、どうすればよいでしょうか?
こちらは「運転記録証明書」というものを取り寄せることで確認できます。
「運転記録証明書」の請求用紙は最寄りの交番・警察署・自動車安全運転センター事務所でも貰うことができます。必要事項を記入し郵便局か、自動車安全運転センター事務所の窓口で申し込みましょう。(安全運転センターに直接持って行っても、すぐには発行してくれないので注意)。
〒郵便局で手続きする場合
運転記録証明書1通670円+郵便局手数料203円=873円払えば、後日自宅に届きます。
家族が「家族滞在」や「留学」ビザ等で28時間以上働いている場合
「家族滞在」や「留学」ビザを家族が持っている場合も注意しましょう。
これらのビザは原則働いてはいけないということになっています。
ですが”資格外活動許可”というものを得ることで週28時間まで働くことができるようになります。この資格外活動許可の週28時間の制限を超えて働いてしまうのもダメです。②”日常生活や社会生活において違法な行為や風紀を乱す行為をくりかえし行っていないこと”に反するので、永住の許可が下りなくなります。
もし週28時間以上働いてしまっていたら?
もし週28時間の制限以上働いてしまっている場合は、いまから週28時間の制限内で働くようにしましょう。
そして5年間法令に反しない就労実績をしっかりと残して永住申請をしましょう。
3. 少年法24条の保護処分が継続中でない者
第二十四条 家庭裁判所は、前条の場合を除いて、審判を開始した事件につき、決定をもって、次に掲げる保護処分をしなければならない。ただし、決定の時に十四歳に満たない少年に係る事件については、特に必要と認める場合に限り、第三号の保護処分をすることができる。
一 保護観察所の保護観察に付すること
二 児童自立支援施設又は児童養護施設に送致すること。
三 少年院に送致すること。
少年法 第二十四条より
文字通り、少年法24条に規定される保護処分が継続中でないことが要件となります。
定住者が永住申請する際の独立生計要件
永住のための2つ目の要件である「独立生計要件」です。
出入国在留管理庁の「永住許可に関するガイドライン」によれば、次のようなものとされています。
② 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和元年5月3日改定)」より
こちらをフレーズごとに区切り、定住者から永住申請する際に必要な独立生計要件をくわしく見ていきましょう。
公共の負担になっていないこと
まず、公共の負担になってないということが記されていますね。
たとえば「生活保護」などを受給している場合は、独立生計要件を満たしていないとされ、永住許可が下りません。
将来において安定した生活が見込まれること
こちらに関しては、年収が過去5年にわたって300万円以上あるかどうかが重要になります。
この金額は、扶養家族の人数によって変わってきます。
転職は審査に影響するの?
転職そのものについては審査に影響しません。
たとえば、転職によって給与が上がったようなケースはむしろ積極的に評価されます。
問題なのは次のようなケースです。
転職して給料や役職が下がってしまうケース
それは、転職したが給与や役職が変わらない場合。あるいは下がってしまうケースです。
「将来において安定した生活が見込まれること」に該当しないとみなされる可能性が高くなります。つまり、安定した生活を送る見込みないだろうと思われるのです。
まず転職した会社で満一年間ほど勤め、働いて生活したという実績を残しましょう。給料も上がるとより良いです。そうした事実を積み上げることで、「将来において安定した生活を送る見込み」を高めていくことができます。
扶養人数が多い場合は大丈夫?
何人扶養しているか、どのように扶養しているのかという扶養人数も重要な判断要素となります。
収入が多くても扶養している人数が多いと生活に使えるお金が減ります。また日本の制度上、扶養している人数が多いほど所得税や住民税などが低くなります。そのため、納税面では日本にあまり貢献していないと判断されます。このことは、③の「国益適合要件」においても問題となってきます。(国益適合要件については次回の記事で解説します)。
永住の申請者に扶養家族がいる場合、先ほど示した年収の300万円よりも多くの収入が必要とされます。
具体的には、以下の通りの年収額が必要になってきます。
必要となる年収額
300万円+(扶養している人数×70万円)
これ以上の収入がなければなりません。具体的な例としては以下の通りになります。
たとえば…
〇妻を一人扶養しているなら、必要となる年収は370万円くらいです。
〇妻と子供、それから親を一人扶養していれば必要となる年収は510万円がおおよその目安となります。
必要となる年収額はあくまでも最低でもこれくらい必要となるという目安です。
もちろん、より多いことに越したことはありません。
事実と異なる扶養に注意
できるだけ税金の額を減らそうとするため、自分の国に残した両親や兄弟を扶養に入れている方がいます。このこと自体はルールを守ったうえで行うぶんには問題ありません。
しかし、実際に両親がまだ現役で働いていたり、十分な収入があったりする場合で、ご自身の税金を減らすために扶養に入れるのはダメです。また、まったく国際送金をしていない場合もダメです。
このように適正な申告や納税をしていない外国人が問題視され、2016年から「親族関係書類」と「送金記録」などの書類を提出しないと扶養控除ができない制度に変わりました。それ以前には名前を書けば扶養控除ができました。そのために2016年より以前の扶養人数に関して適正な扶養であるかどうか、海外の親族との関係や状況、送金記録の説明や提出を求められたりします。
このようなことをしていた場合はどうすればいいでしょうか?
「修正申告」といって、さかのぼって扶養を外し、控除されていた分の税金を納める必要があります。
永住を考えているのであれば、必ず永住申請の前に済ましておきたい手続きとなります。
申請人本人が主婦/主夫である場合は?
申請人本人が主婦/主夫の方で、働いていない場合。同居している配偶者が独立生計要件を満たしていれば許可が下りる可能性があります。このような場合、必ずしも申請人本人が独立生計要件を備えている必要はありません。
定住者が永住申請する際の国益適合要件
永住のための要件である「国益適合要件」は、出入国在留管理庁の「永住許可に関するガイドライン」によれば、次のようなものとされています。
③ その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税,公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
ウ 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和元年5月3日改定)」より
ですが、定住者から永住申請する際に求められる国益適合要件は、基本的な永住申請のパターンとは少し異なり緩和されている部分があります。
それでは見ていきましょう。
①定住者の在留資格を許可されてから引き続き5年以上日本に在留していること
これは日本継続在留要件といいいます。
定住者の在留資格を許可され引き続き5年以上日本に在留を続けていること。これが要件となってきます。日本に居住して5年経てばよいわけではないので注意しましょう。その5年の間に一度でも定住者の在留資格が途切れてしまうとダメです。
長い期間日本から出国している場合
- 1回の出国で3か月以上出国。
- 1年間で100日以上出国。
いずれかに該当する場合、引き続き在留しているという要件から外れる可能性が高いです。出産や出張で日本を離れなければならない場合などが該当します。このような場合には、出国の理由や期間が長くなった理由などを合理的、整合的に説明することが必要となってきます。
「日本人の配偶者等」の在留資格から相手との離婚や死別で「定住者」に変更した方
日本人と結婚して、「日本人の配偶者等」の在留資格で在留していた方が、パートナーと離婚した場合、あるいはパートナーが亡くなって死別した場合、「定住者」の在留資格が許可されることがあります。
このようなケースで「日本人の配偶者等」から「定住者」の在留資格へ変更申請した場合、「日本人の配偶者等」で在留していた期間と「定住者」で在留した期間を合わせて5年間引き続き在留していれば、この要件に該当するとみなされます。
②納税義務を果たしていること
つまり税金をちゃんと支払っているかどうか、ということをきいています。
ここでいう税金とは、住民税、国民年金、国民健康保険税などを指しています。
会社員の方は、会社で社会保険に加入している場合が一般なので給料から天引きされている方がほとんどです。
中には天引きされていない方もいるので注意が必要です。
その場合には、払っているのは当然として、納付期限までにしっかりと納付しているかということが問題になります。
これを証明するために、永住申請の際に納付書についている領収書を提出しますので保管しておきましょう。銀行引き落としの場合は、通帳の履歴のコピーを提出しますので記帳を忘れないようにしましょう。
もしも納付期限を超えてしまっていることがある場合
永住申請する前の直近2年間、納付期限をしっかりまもって支払ったという実績を残しましょう。
そして、別途理由書において納付期限が遅れていた理由と反省、それから反省を踏まえたこれからの対策方法を記して申請すれば許可される可能性もあります。
③「定住者」の在留資格で3年以上の期間の在留許可を得ていること
法律上5年が最長の在留許可になっています。
ですが現在「定住者」として3年以上の在留許可を得ていれば問題ありません。
④公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないことが求められています。
これは具体的な病名を挙げれば以下のものなどです。
公衆衛生上の観点から有害となるおそれのあるもの
〇麻薬・覚せい剤・大麻等の慢性薬物中毒者
〇クリミア・コンゴ出血熱 痘そう 南米出血熱 ラッサ熱のウイルス性出血熱 ペスト マールブルグ病等の一類感染症
〇ポリオ 結核 ジフテリア SARS MERS 鳥インフルエンザ等の二類感染症、指定感染症、新感染症等の罹患者
⑤著しく公益を害する行為をするおそれがないと認められること
具体的には次の3つになります。
- 日本国の法令に違反して、懲役・禁錮または罰金に処せられたことがないこと
- 日常生活、社会生活において、違法行為または風紀を乱す行為を繰り返し行っていない者
- 少年法による保護処分が継続中でないこと
これらに該当しないことが必要です。
⑥身元保証人がいること
他の在留資格から永住申請する場合と同様、身元保証人が必要になります。
身元保証人にはどのような人がなれるのでしょうか?
日本人か「永住者」の在留資格で在留する外国人のみがなれます。
会社の上司や、昔通っていた学校の先生。あるいは結婚しているパートナーの方などに引き受けてもらうことが多いですね。