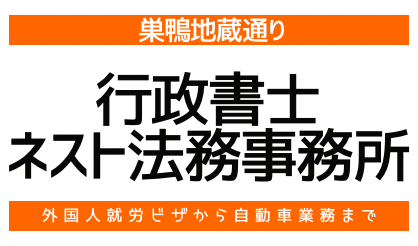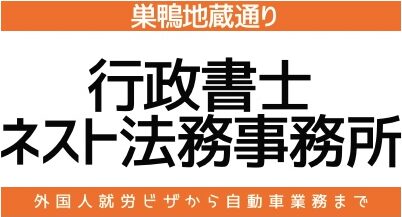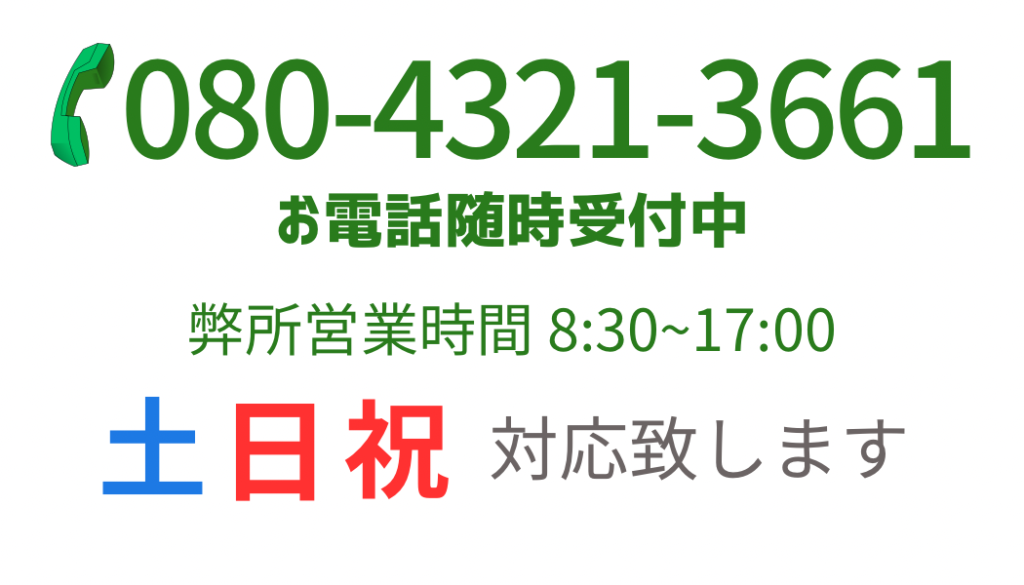なぜ特殊車両通行許可が必要となるのか根拠となる法律はこれだ!

特殊車両通行許可の根拠法
特殊車両通行許可とは、法令で定められている一般的制限値を超える規格を有する車両が、公道を走行する際にあらかじめ取得しておくべき許可となります。
しかしながら、なぜ一般的制限値を超過する車両は特車通行許可を取得する必要があるのか、理解している関係者は意外にも少ないのではないでしょうか。
この記事で根拠となる法律の理解を深めておき、道路事務所との調整やトラブルが起きた際に対応できるように構えておきましょう。
道路法第1条における目的
道路法第1条(目的)
この法律は、道路網の整備を図るため、道路に関して、路線の指定および認定、管理、構造物、保全、費用の負担区分等に関する事項を定め、持って交通の発達に寄与し、公共の福祉を増進することを目的とする。
特殊車両通行許可の根拠となる道路法第1条には道路法の目的が記されています。
道路法の目的は、道路網の整備を図り、整備することを通して、交通発達や公共福祉を増進することが目的とされています。
整備するために必要な保全行為や費用を負担しろとも書かれています。
20tを超える特殊車両が何台も連日走行すると、アスファルトといえ痛んできます。すると道路環境が悪くなり事故を誘発してしまいます。それを避けるために補修などを行いますが当然費用が発生します。
道路法第46条 通行の禁止又は制限
道路法第46条(通行の禁止又は制限)
道路管理者は、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、区間を定めて、道路の通行を禁止し、又は制限することができる。
一 道路の破損、欠損その他の事由により交通が危険であると認められる場合
二 道路に関する工事のためやむを得ないと認められる場合
道路法第46条は、特殊車両通行許可申請が不許可になる場合の根拠です。
道路構造を保全する、交通の危険を防止するために、通行の禁止や制限ができるという条文です。
道路法第47条 一般的制限値
道路法第47条
道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路との関係において必要とされる車両の幅、重量、高さ、長さおよび最小回転半径の最高限度は、政令で定める。
道路法第47条は特殊車両通行許可が必要となる条件の「一般的制限値」についての根拠となります。
ここで言われる政令は、車両制限令であり一般的制限値の詳細はこちらで定められています。
道路法第47条の2 限度超過車両の通行の許可等
道路法第47条の2
道路管理者は、車両の構造又は車両に積載する貨物が特殊であるためやむを得ないと認めるときは、前条第2項の規定又は同条第3項の規定による禁止若しくは制限にかかわらず、当該車両を通行させようとするものの申請に基づいて、通行経路、通行時間等について、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要な条件を付して、同条第1項の政令で定める最高限度又は同条第3項に規定する限度を超える車両の通行を許可することができる。
道路法第47条の2は特殊車両通行許可の核となる条文となっています。一般的制限値を超過する車両について通行を許可する旨が記されています。