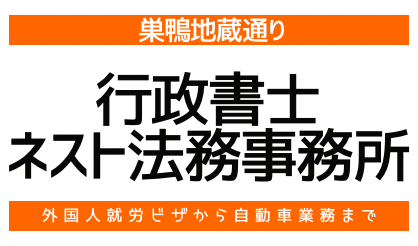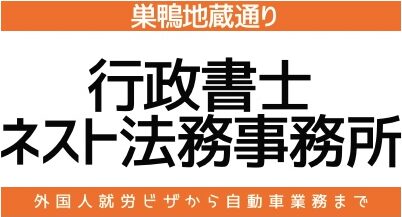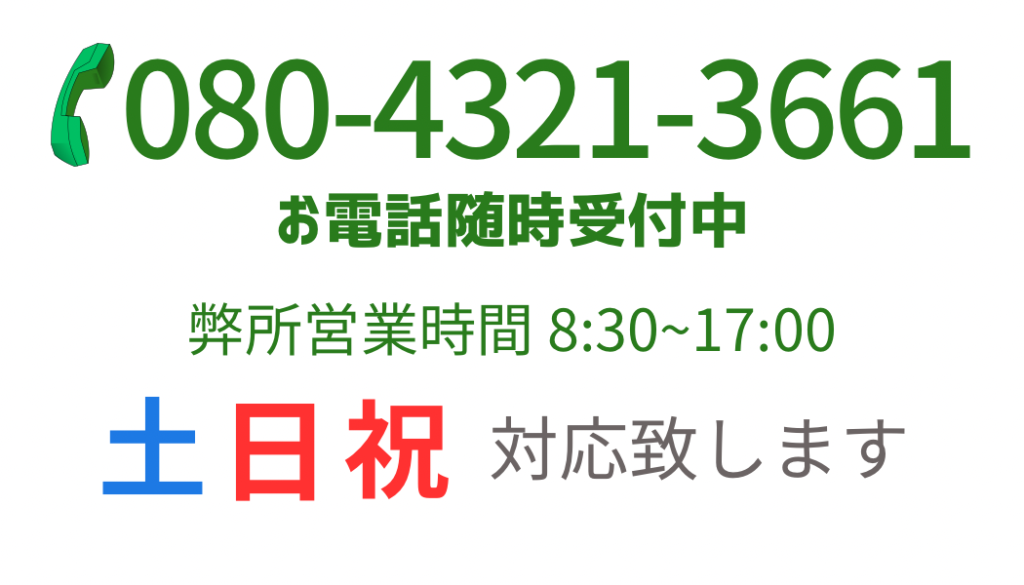酒類販売業・卸売業免許の概要
酒類販売業・卸売業免許の概要
お酒の小売や卸売など、酒類販売業を開始するにはあらかじめ税務署から酒類販売業免許を取得する必要があります。
お酒をネット販売する場合や、海外へ輸出販売するケースでもこちらの免許が必要です。
酒類販売業免許は継続的にお酒を販売するための免許で、取り扱う酒の種類に対応した免許があります。
これらの免許を取得することで、一般顧客だけでなく、飲食店や菓子製造社など、酒類販売業免許を持っていない事業者へ酒を販売することができます。
尚、酒類を酒類販売業者や酒類製造業者へ販売する場合は酒類卸売業免許の取得が別途必要となります。
申請先
酒類販売業として営業をはじめるには、販売場の住所を管轄する税務署から酒類販売業免許を受ける必要があります。
酒類販売業免許は、原則販売場ごとに免許取得が必須です。そのため主たる営業所で免許を取得している場合でも支店等を開設する場合は別途、免許の取得が必要となります。
無免許で販売または卸売した場合の罰則
酒類販売業・卸売業免許を取得せず、無免許で酒類を販売または卸売した場合、酒税法により1年以下の懲役または50万円以下の罰金が定められています。尚、虚偽の申請や不正行為によって免許を受けた場合、免許取り消しや営業停止処分が下されます。
酒類販売・卸売営業をする場合は必ず免許を取得するようにしてください。
酒類販売業免許の要件
酒類販売業免許には要件が設けられています。具体的に審査される項目としては、申請者、申請者の法定代理人、申請法人の役員、申請販売場の支配人および申請販売場です。これらが以下の各要件を満たしていることが必要となります。
尚、申請書類のうちに免許要件誓約書が含まれており、虚偽の記載や不正行為が発覚した場合、免許の拒否処分あるいは免許取り消しとなるので覚えておきましょう。
申請者の人的要件
この要件は免許申請者にかかる要件で以下のとおり6つが定められています。
- 申請者が酒類等の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消 処分を受けた者である場合には、取消処分を受けた日から3年を経過していること
- 申請者が酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処 分を受けたことがある法人のその取消原因があった日以前1年内にその法人の業務を執行す る役員であった者の場合には、その法人が取消処分を受けた日から3年を経過していること
- 申請者が申請前2年内において国税又は地方税の滞納処分を受けたことがないこと
- 申請者が国税又は地方税に関する法令等に違反して、罰金の刑に処せられ又は通告処分を受 けた者である場合には、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過していること
- 申請者が、二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律、風俗営業等の規制及び業務の適正化 等に関する法律(20 歳未満の者に対する酒類の提供に係る部分に限る。)、暴力団員による不当 な行為の防止等に関する法律、刑法(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫又 は背任の罪)又は暴力行為等処罰に関する法律の規定により、罰金刑に処せられた者である場 合には、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること
- 申請者が禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること
場所的要件
販売場についての要件は以下のとおりです。
- 正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に販売場を設けようとしていない こと
場所的要件として具体的には次の条件を満たすことを求められます。
- 申請する販売場が、酒類の製造場や酒類の販売場、バーや料理店等と同一区画内ないこと
- 申請販売場における営業が、販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性その他販売行為において他の営業主体の営業と明確に区分されていること
経営基礎要件
経営基礎要件は、経済的な面から見た人的要件です。具体的には以下の要件が求められます。
免許の申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない場合のほか、その経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないこと。
- イ 現に国税又は地方税を滞納している場合
- ロ 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合
- ハ 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っている場合
- ニ 最終事業年度以前3事業年度の全ての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損を生じている場合
- ホ 酒税に関係のある法律に違反し、通告処分を受け、履行していない場合又は告発されている場合
- へ 販売場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整 備に関する法律その他の法令又は地方自治体の条例の規定に違反しており、店舗の除却又は移転を命じられている場合
- ト 申請販売場において、酒類の適正な販売管理体制が構築されないことが明らかであると見込まれる場合
- チ 経験その他から判断し、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人であること
- 免許を受けている酒類の製造業若しくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く。)の業務に引き続き3 年以上直接従事した者、調味食品等の販売業を3年以上継続して経営している者又はこれらの業務に 従事した期間が相互に通算して3年以上である者。
- なお、これらの従事経験や経営経験がない場合には、その他の業での経営経験に加え「酒類販売管 理研修(17 頁参照)」の受講の有無等から、1酒類の特性に応じた商品管理上の知識及び経験、2酒 税法上の記帳義務を含む各種義務を適正に履行する知識及び能力等、酒類の小売業を経営するに十分 な知識及び能力が備わっているかどうかを実質的に審査することになります。
- 酒類業団体の役職員として相当期間継続して勤務した者又は酒類の製造業若しくは販売業の経営者として直接業務に従事した者等で酒類に関する事業及び酒類業界の実情に十分精通していると認められる者。
- リ 酒類を継続的に販売するために必要な資金、販売施設及び設備を有していること、又は必要な資金を有し免許を付与するまでに販売施設及び設備を有することが確実と認められ ること
需要調整要件
需要調整要件は、酒税をしっかりと徴収するために、明確に酒類販売業として売買をしたかどうかが判別できるような条件を完備しているかを求めている要件となります。具体的には以下のとおりです。
- 酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合に該当しないこと
需要調整要件は、具体的には以下の2点を満たすことが必要です。
- 設立の趣旨からみて販売先が原則としてその構成員に特定されている法人又は団体ではないこと
- 酒場、旅館、料理店等酒類を取り扱う接客業者でないこと
酒類販売業免許の種別
一般酒類小売業免許
一般酒類小売業免許は、一般顧客だけでなく店舗で酒類を提供する事業者、菓子等製造業者に対し酒類を継続的に販売することができる免許です。
原則、一般酒類小売業免許を取得することで、すべての種類の酒類を、販売場において、小売することができます。
そのため、販売場を保有していることが大きな要件となっています。
通信販売酒類小売業免許
通信販売酒類小売業免許は、通信販売によって酒類を小売することができる酒類小売業免許です。
通信販売とは、インターネットやカタログ送付などで商品の内容や価格、郵送条件などを提示し、電話やメールなどで売買契約の申し込みなどを受けて販売する方法です。
通信販売の場合は、販売場は必須ではないので店舗などは不要です。
酒類卸売業免許の種別
全酒類卸売業免許
全酒類卸売業免許は、全ての種類の酒類を卸売することができる免許です。
全酒類卸売業免許は各免許年度毎に、免許を与える件数を卸売販売地域ごとに算定し、免許可能件数の範囲内で免許を付与等することとしています。
特定の卸売業免許は、各申請年度毎に決められた件数の免許を付与することとなっています。
そのため公開抽選を行い、免許審査の順番を決定した上で審査を行なっていき、基準をクリアした場合に順番毎に免許を付与していきます。一定数に達した場合は、その申請年度には免許が付与されません。
ただし、免許の件数に限りがあるのは、「全酒類卸売業免許」および「ビール卸売業免許」のみです。
ビール卸売業免許
ビール卸売業免許はビールのみ卸売できる免許です。
注意しなけばならないのは、いわゆる第三のビールはビール卸売業免許で卸売することができない点です。
第三のビールは洋酒卸売業免許で卸売が可能です。
洋酒卸売業免許
洋酒卸売業免許は果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、その他の醸造酒、スピリッツ、リキュール、粉末酒、雑酒の全ての卸売業が可能となる免許です。
これらの酒類の品目のうち複数の酒類を卸売することも可能です。
輸出入卸売業免許
輸出入卸売業免許は、免許を保有している者が輸出または輸入する酒類を卸売することが可能な免許です。
注意点としては、他人が輸出入した酒類は対象外となります。
店頭販売卸売業免許
店頭販売卸売業免許は、自店舗の会員である酒類販売業者に対して店頭において酒類を販売し、直接持ち帰るという方法によって卸売ができる免許となっています。
- 会員制であること
- 店舗で販売すること
- 直接持ち帰ること
この3つが注意すべき点となります。
協同組合員間卸売業免許
協同組合員間卸売業免許は、免許保有者が所属する協同事業組合員である酒類販売業者へ酒類を卸売する場合に必要な免許です。
自己商標卸売業免許
自己商標卸売業免許とは、免許保有者が開発した商標または銘柄の酒類のみを卸売することができる免許です。
特殊酒類卸売業免許
特殊酒類卸売業免許とは、以下のような酒類販売事業者の特別な必要に応じるために酒類の卸売を行う場合に必要となる免許です。
- 酒類製造者の本支店、出張所等に対する酒類卸売業免許
- 酒類製造者の企業合同に伴う酒類卸売業免許
- 酒類製造者の共同販売機関に対する酒類卸売業免許
料金表(税込)
| 免許種別 | 料金(税込) |
|---|---|
| 一般酒類小売業免許 | ¥99,000 |
| 通信販売酒類小売業免許 | ¥88,000 |
| 酒類卸売業免許 | ¥ |
- 税務署への登録免許税として実費¥30,000がかかります。
酒類販売業免許取得サポートの流れ
当事務所へお任せいただければ、事前相談から申請書、図面や事業計画作成はもちろんのこと、税務署との調整まで徹底サポート致します。
酒類販売業の実務経験者がいない場合
酒類小売業免許の要件として、3年以上の酒類の販売経験や経営経験が設けられています。
仮にこうした経験がなくとも、「酒類販売管理研修」を受講、修了することで、この実務経験に代えることでき、要件を満たすことができます。
よくあるQ & A